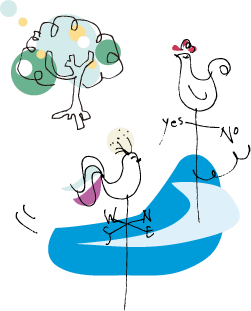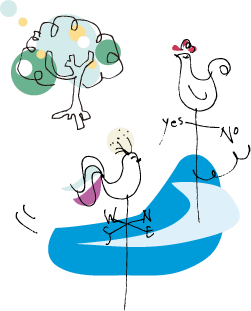 「降りやまぬ雨はない」というが、今や少しでも湿気を感じれば、期待を込めて窓の外を見る。東三河地方に水を供給する豊川用水で渇水が続いている。
「降りやまぬ雨はない」というが、今や少しでも湿気を感じれば、期待を込めて窓の外を見る。東三河地方に水を供給する豊川用水で渇水が続いている。
今月初め、行きつけのガソリンスタンドで洗車を頼もうとしたら、節水対策で中止していた。美容院では、水が使えなくなれば「休業するしかない」と危機感をにじませる。
豊川本流からの取水が始まり、25日はまとまった雨となった。あとは神頼みか。
さかのぼると2013年の夏、豊川市に「雨男」が現れた。旧東海道赤坂宿で江戸時代から続くとされる「雨乞い祭り」に、演歌歌手の山川豊さんが招かれたのだ。自他ともに認める雨男だそう。普段は疎まれる「特性」かもしれないが、このときばかりは大歓迎だった。
がんで闘病中と聞いたが、公演を再開し、デビュー45年の節目となる今年は、通年で活動されるという。水不足の地に「恵みの雨」をもたらしてくれることを期待している。